
展覧会のテーマ
この展覧会はポップアートを肯定する立場にあります。
「ポップは絵画を肯定する。だが絵画にプレッシャーをかけもする」と美術評論家、ハル・フォスターは評しています。
この立場に同意で、彼が危惧していた事象が現代の状況も含みながら表顕していると感じます。
文明の進化、人々の対応により消費活動が簡素で、手軽になっています。
アートにおいても市場にある以上例外ではなく、手垢の付いた表現に対して危機的な圧力をかけています。
無論、一口にアートといえど多くのジャンル、表現方法が存在するため一概には断定しかねるますが、社会や文明が変化すればそれに呼応して変容してきたことも事実です。
近年、アート界を見渡すと絵画のイラスト化が顕著に見られ、マーケットに於いても同様のことがいえます。
情報過多になっている社会実情のアンチテーゼにあたるのか
ファーストインプレッションで引き付けることを命題とせれているからなのか
ポップミュージックに於いても同じく、イントロに所要する平均時間が年々短くなっているという
このような現状は定数とし、変数に挑む3名の作家
赤羽由衣は作品に成される場面の選びかた、変容させ方に魅力を感じる
都市生活によく見られる同意性、同調性、理解の及ばないものに対する態度
誰もが経験し、脳内にて同場面を反芻し考えるであろう場面を赤羽はウィットに変幻させ表現する
森本来実はぬいぐるみやおもちゃに愛着があり、それを愛で表現することで自らの内心にある幼児性に接続する。慈愛を求めて幼児性を保持し続ける。そんな救いや願いを込めて表現している。
誰しも立場や、環境により表立っては大人の顔を形成するが、そんな中にも幼児性を隠し持っているはずではないだろうか。
故郷に帰り、ノスタルジックな情景や音、香りにより子供時分にトリップした経験はあるのではないだろうか。
森本来実の作品はそのような自身の時間軸を旅させてくれるきっかけを与えてくれるのでないでしょうか。
山口京将は少年の頃、母との何気ない会話からジョークにより空想にて独自の世界観を構築するきっかけとなる。
「お母さんね、ベランダでね人間の顔した鳥、見たよ」
この一言が、以後、山口少年に多大なる空想と期待と妄想をもたらす。
彼は悶々と邂逅を待っている。
いつ、その鳥と出会えるのか、そして結局は叶わない、その空白を作品を作ることで埋めている
成長し作品を作るようになった時、母に当時のことを聞くと、母はそのような会話をした覚えがなかった
かくもオトナとは、、
山口は現在も少年の頃にイメージした不可思議な鳥を追いかけつつ、揺るがない存在感を示し続けている。
さて、2020年代に変幻するアートはどのように変容を遂げ次世代へと血脈をつなげるのだろう
この問いについて、赤羽由衣、森本来実、山口京将の3名のアーティストはどのような“今”と“未来”を見せてくれるのでしょうか
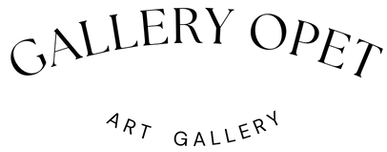.png)